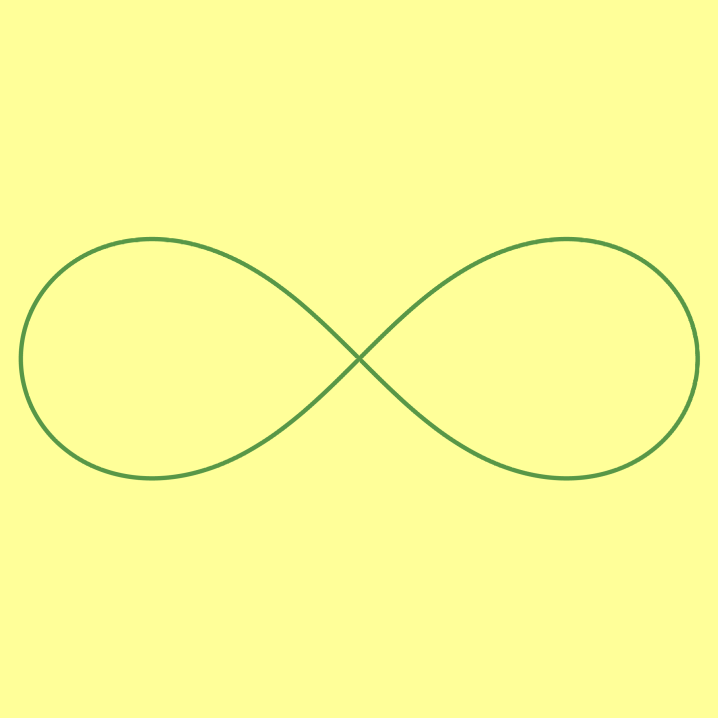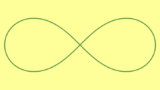留数の表記の問題点
留数は \(\mathop{\rm Res}\limits_{z=c} f(z) \) などのように記述されるが、\(\mathop{\rm Res}\limits_{z=c} f(z)\,dz\) のように微分形式に対応させるべきという見解もある。留数 \(\mathop{\rm Res}\limits_{z=c} f(z) \) は \(z=c\) の周囲で積分した値なので一理ある考え方である。複素関数入門(神保道夫)では留数の記号に微分形式を使用している。複素関数論講義(野村隆昭)では記号が混在している。紛らわしくない場合は省略しているのだろう。
どちらの教科書も微分形式を利用することで変数変換における誤りを防げることを主張している。例として \( f(z)=\frac{4}{4z^2-1} \) を \(z=\frac{1}{2} \) の周囲 \(C:|z-\frac{1}{2}|=\frac{1}{2} \) で積分してみよう。留数定理より、\( \displaystyle \frac{1}{2\pi i}\int_C f(z)\, dz = \mathop{\rm Res}\limits_{z=\frac{1}{2}}\frac{4}{4z^2-1} = 1 \) となる。原点における留数にして計算しようとして変数変換 \( \zeta=2z-1 \) とした場合、 \( \displaystyle \mathop{\rm Res}\limits_{z=\frac{1}{2}}\frac{4}{4z^2-1} = \mathop{\rm Res}\limits_{\zeta=0} \frac{4}{\zeta^2+2\zeta} =2 \) と誤りが懸念される。積分における変数変換 \( \displaystyle \frac{1}{2\pi i}\int_C \frac{4}{4z^2-1}\, dz = \frac{1}{2\pi i}\int_{C’} \frac{4}{\zeta^2+2\zeta} \, \frac{d\zeta}{2} \) を見れば
\( \begin{eqnarray}
\mathop{\rm Res}\limits_{z=\frac{1}{2}}\frac{4}{4z^2-1}\,dz &=& \mathop{\rm Res}\limits_{\zeta=0} \frac{4}{\zeta^2+2\zeta} \frac{d\zeta}{2}
\end{eqnarray} \)
のように微分形式を使った記述が適切だと納得がいく。この表記は無限遠点における留数を議論するときにも便利である。
無限遠点における留数
ある \(R>0\) に対して、\(R<|z|<\infty\) で \(f(z)\) が正則な場合、\(z=\infty\) は \(f(z)\) の孤立特異点であるという。この時 \(f(\frac{1}{w})\) は \(0<|w|<\frac{1}{R}\) で正則なので、 \( w=0 \) は \(f(\frac{1}{w})\) の孤立特異点である。以下、\(z=\infty\) は孤立特異点と仮定する。無限遠点の留数を次のように定義する。
\(\begin{eqnarray}
\mathop{\rm Res}\limits_{z=\infty} f(z)\,dz
&=& \mathop{\rm Res}\limits_{w=0} f\left(\frac{1}{w}\right)\,d\left(\frac{1}{w}\right)
= – \mathop{\rm Res}\limits_{w=0} f\left(\frac{1}{w}\right)\,\frac{dw}{w^2}
\end{eqnarray}\)
この定義では \( \displaystyle \mathop{\rm Res}\limits_{z=\infty} f(z)\,dz \) は \(f(\frac{1}{w})\) の留数にはならない。\(R<|z|<\infty\) におけるローラン展開 \( \displaystyle f(z) = \cdots + \frac{a_{-1}}{z} + a_0 + a_1 z + \cdots \) との関係を見よう。
\( \begin{eqnarray}
\mathop{\rm Res}\limits_{z=\infty} f(z)\,dz
&=& – \mathop{\rm Res}\limits_{w=0} \left( \cdots + a_{-1}w + a_0 + a_1 \frac{1}{w} + \cdots \right) \frac{dw}{w^2} \\
&=& – \mathop{\rm Res}\limits_{w=0} \left( \cdots + \frac{a_{-1}}{w} + \frac{a_0}{w^2} + \frac{a_1}{w^3} + \cdots \right) \, dw
\end{eqnarray} \)
\( \displaystyle \mathop{\rm Res}\limits_{z=\infty} f(z)\,dz = -a_{-1} \) と分かる。
\(z=\frac{1}{w}\) と置き換えて実際に積分をするときには、積分路の向きに注意しなければならない。原点を中心とする半径 \(r > R\) の円周上で反時計回りの積分を考えよう。
\(\begin{eqnarray}
\int_{|z|=r} f(z)\,dz
&=& – \int_{|w|=\frac{1}{r}} f\left(\frac{1}{w}\right)\,\frac{dw}{w^2} \\
\end{eqnarray}\)
となるが、\(z=re^{i\theta}\) とおくと \(w=\frac{1}{r}e^{-i\theta}\) となるので、\(w\) に関する積分路は時計回りになっている。反時計回りにすれば符号は逆になるので、
\(\begin{eqnarray}
\frac{1}{2\pi i}\int_{|z|=r} f(z)\,dz
&=& – \mathop{\rm Res}\limits_{z=\infty} f(z)\,dz \\
\end{eqnarray}\)
となる。\(|z|<R\) における \(f(z)\) の極を \( \left\{ c_1,c_2,\cdots,c_n \right\} \) とすると、左辺は \( \displaystyle \sum_{k=1}^n \mathop{\rm Res}\limits_{z=c_k} f(z)\,dz \) となるから、上で導出した式は
\(\begin{eqnarray}
\sum_{k=1}^n \mathop{\rm Res}\limits_{z=c_k} f(z)\,dz + \mathop{\rm Res}\limits_{z=\infty} f(z)\,dz
&=& 0
\end{eqnarray}\)
となり、無限遠点を含めた全複素平面での留数の総和が 0 となる。定義として採用した理由はここにあるのかな。
簡単な計算例
簡単な例を計算したところやらかして解決まで手間取ってしまったので、自戒の意味も込めて記録しておく。単純な例として \(f(z)=\frac{1}{z}\) の場合、 \( \mathop{\rm Res}\limits_{z=0} f(z)\,dz = 1,\, \mathop{\rm Res}\limits_{z=\infty} f(z)\,dz = -1\) である。確かに留数の総和は 0 になっている。また、\(f(\frac{1}{w})=w\) であり、無限遠点は除去可能な特異点であるが留数は 0 ではない。
次に、\( g(z)=\frac{1}{1-z} \) を考えよう。 唯一の極 \(z=1\) での留数は \(-1\)。\( \frac{1}{1-z} = 1+z+z^2+\cdots \) だから \(\frac{1}{z}\) の項がなくて、無限遠点での留数は 0? 留数の総和が 0 にならなくておかしい。何を見落としているのか。しばらく悩んでしまった。
見落としていたのは単純で \(|z|>1\) におけるローラン展開を求めるべきだったのだ。
\( \begin{eqnarray}
\frac{1}{1-z}
&=& \frac{-1}{z}\frac{1}{1-\frac{1}{z}} \\
&=& \frac{-1}{z} \left( 1+\frac{1}{z}+\frac{1}{z^2}+\cdots \right) \\
&=& -\frac{1}{z}-\frac{1}{z^2}-\frac{1}{z^3}+\cdots \\
\end{eqnarray}\)
これで無限遠点における留数は 1 となり、留数の総和も無事 0 となった。初歩的なミスであったが、複数の視点から検証することの重要性を改めて感じさせられた。