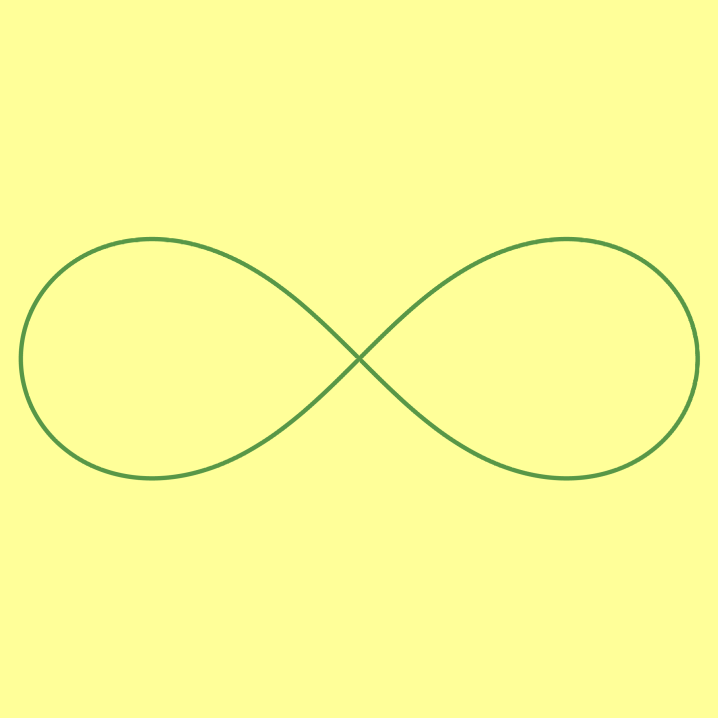分数イデアル、特に逆イデアルについて学んだことを記録。デデキント聖域における素イデアル分解の一意性の証明に使われる。
分数イデアル
\(R\) を整域、\(K\) をその商体とする。\(K\) の部分集合 \(I\) が次の条件を満たすとき、\(R\) の分数イデアルという。
(1) \(I\) は \(K\) の \(R\) 部分加群である。
(2) \( \gamma I \subset R \) となる \(\gamma \in R\) が存在する。
分数イデアル \(I_1,I_2\) に対して、\(I_1+I_2,\, I_1I_2,\, I_1\cap I_2\) も分数イデアルである。また (1) と \(1\in R\) より、任意の分数イデアル \(I\) に対して、\(IR=I\) である。\(a\in K^{\times}\) に対して \((a)=aR\) は分数イデアルで、単項イデアルという。 特に、\((a)(a^{-1})=R\) が成り立つ。これは \((a^{-1})\) が \((a)\) の逆イデアルであることを意味するのだが、これを一般の分数イデアルに拡張したい。
イデアル商
分数イデアル \(I,J\) に対して、\(I:J=\{ x \in F ; xJ \subset I\}\) と定義し、イデアル商という。イデアル商が分数イデアルであることを示す。
(1) 部分加群であることは易しい。\(R\)部分加群であることを示す。\(J\) は \(R\) 部分加群だから \( \alpha\in R\) に対して、\(\alpha J \subset J\) が成り立つ。\(x\in I:J\) に対して、\(\alpha x J = x (\alpha J) \subset x J \subset I \) だから、\(I:J\) は \(R\) 部分加群である。
(2) \( \gamma I \subset R\) となる \(\gamma \in R \) が存在する。定義より \(x\in I:J \Leftrightarrow xJ \subset I \) だから、\( \gamma x J \subset \gamma I \subset R \) より、\( \gamma (I:J) \subset R \) が成り立つ。
逆イデアル
分数イデアル \(I\neq (0)\) に対して、\(I^{-1}=R:I\) と定義し、\(I\) の逆イデアルという。定義より、\(I^{-1}I \subset R\) が成り立つ。\(I^{-1}I=R\) が成り立つとき、\(I\) を可逆イデアルという。逆イデアルは存在するのに、可逆イデアルでない場合があるとは、紛らわしい用語である。調べた範囲では、可逆でない例は見つからなかった。
\(J\) が可逆であっても、\( IJ = R \Rightarrow I=J^{-1}\) は明らかでないので、ここで示す。仮定と逆イデアルの定義から \(I\subset J^{-1}\) が成り立つ。\(I\supset J^{-1}\) を示す。定義より、\(J^{-1}J\subset R\)。
\( I=IR \supset I J^{-1} J \supset J^{-1}R = J^{-1}\)
よって、\( IJ = R \Rightarrow I=J^{-1}\) が証明された。
定義から簡単に分かる性質を列挙する。
(1) \((0)\) でない分数イデアル \(I \subset J \) に対して、\( I^{-1} \supset J^{-1} \)
(2) \(a\in K^{\times}\) に対して、\( (a)^{-1} = \left( a^{-1} \right) \)
ネーター整域
\(0\) でない分数イデアルに対して逆イデアルは存在するが、可逆性は不明であった。一般には成り立たないようで、デデキント整域なら成立する。ここではデデキント整域より弱いネーター整域における性質を示す。
(補題1) \(I\) をネーター整域 \(R\) の \((0)\) でない整イデアルとする。有限個の \((0)\) でない素イデアル \(P_1,\cdots,P_r\) が存在して、\( P_1\cdots P_r \subset I \) と出来る。
(証明) 素イデアル \(P\) 及び 整イデアル \( J_1,J_2\) に対して \(J_1,J_2 \subset P \) ならば、\(J_1\subset P\) または \(J_2\subset P\) である。実際、\(J_1\not\subset P\) とすると、 \( a\not\in P\) である \(a\in J_1 \) が存在する。任意の \( b\in J_2\) について \(ab\in P\) だから、\(b\in P\) であり、\(J_2\subset P\) となる。(ここまでは任意の整域で成り立つ)
\(I\) が素イデアルであれば、それ自身が1つの素イデアルの積だから、素イデアルでないとすると、\(bc\in I, b\not\in I,c\not\in I\) となる \(b,c \in R\) が存在する。\(B_1=I+(b), C_1=I+(c) \) とおくと、\(B_1\supsetneq I,C_1\supsetneq I\) かつ \(B_1C_1=I^2+bI+cI+(bc) \subset I\) である。もし、\( B_1,C_1\) の両方が有限個の素イデアルの積を含むならば、補題の主張は成り立つ。少なくとも一方、例えば \(B_1\) がそうでないとしよう。このとき、\(I\) 同様に \(B_1\) も素イデアルではないことに注意しよう。\(B_1\) に同じ議論を繰り返し、\(B_2C_2 \subset B_1 \) が得られたとする。\( B_2,C_2 \) の両方が有限個の素イデアルの積を含むならば、\(B_1\) が有限個の素イデアルの積を含まないことに矛盾する。したがって、一方は有限個の素イデアルの積を含まない。\(B_2\) が有限個の素イデアルの積を含まないとする。これを繰り返すと、\(I\subsetneq B_1 \subsetneq B_2 \subsetneq \cdots \) と無限に続くことになり、ネーター性に反する。
デデキント整域
以下の2条件を満たす(体でない)ネーター整域 \(R\) をデデキント整域という。
(1) \((0)\) でない素イデアルは極大イデアルである。
(2) 整閉である。すなわち、\(R\) 係数の単多項式の解は \(R\) に含まれる。
以下では \(R\) はデデキント整域として、\((0)\) でない分数イデアルの可逆性を示す。
次の補題では整閉は必要ない。
(補題2) \((0), R\) でない整イデアル \(I\) に対して、\(I^{-1} \supsetneq R\) が成り立つ。
(証明) 逆イデアルの定義より \(I^{-1} \supset R \) が成り立つ。\(I^{-1}\neq R\) を示す。\(I\ni a (\neq 0)\) を任意に取ると、補題1より
\( P_1P_2\cdots P_r \subset (a) \subset I \subset P \)
となる素イデアル \(P,P_1,P_2,\cdots,P_r\) が存在する。\(P_1P_2\cdots P_r\) は \(r\) が最小になるように取る。補題1の証明の前半を繰り返し適用すると、\(P_1,\cdots,P_r\) のうち1つは \(P\) に含まれる。\(P_1\subset P\) とする。\(P_1\) は極大イデアルだから \( P_r=P \)、則ち \( P_1\cdots P_{r-1} P \subset (a) \subset P \) である。\(r\) の最小性より \( P_1\cdots P_{r-1} \not\subset (a) \) であり、\(b\not\in (a)\) となる \(b\in P_1\cdots P_{r-1}\) が取れる。ここで \( a^{-1}b \not\in R \) である。なぜなら、\(a^{-1}b\in R \Rightarrow b \in aR =(a) \) となり、\(b\) の取り方に矛盾する。
\(a^{-1}b I \subset a^{-1}b P \subset a^{-1} P_1 \cdots P_{r-1} P \subset a^{-1} (a) = R \)
により、\( a^{-1}b \in I^{-1}\) が得られる。したがって、\(I^{-1}\neq R\) である。
(補題3) 極大イデアルは可逆である。すなわち \(P^{-1}P=R\)。
(証明) 極大イデアル \(P\) に対して、補題2より \(P^{-1}\supsetneq R\)。また、逆イデアルの定義より \(P^{-1}P \subset R \)。したがって、\( P =PR \subset P^{-1}P \subset R \)。 \(P\) は極大イデアルだから、\( P^{-1}P \) は \(P\) または \(R\)。\( P=P^{-1}P\) と仮定する。\(a(\neq 0)\in P, x\in P^{-1}\) を任意に取ると、\(ax \in P^{-1}P=P \)。再び、\( ax \in P, x\in P^{-1} \) から \(ax^2 \in P \)。これを繰り返して、任意の \(n\) に対して \( ax^n \in P \) が得られる。イデアルの昇鎖列 \( (a) \subset (a,ax) \subset (a,ax,ax^2) \subset \cdots \) を考えると、ネーター性から \((a,ax,\cdots,ax^{m-1}) = (a,ax,\cdots,ax^m) \) となる \(m\) が存在する。\(ax^m\) が \( a,ax,\cdots,ax^{m-1} \) で生成されるから、\(ax^m = ab_0+ab_1x + \cdots + ab_{m-1}x^{m-1},\, (b_i\in R) \) と表される。\(a (x^m-b_{m-1}x^{m-1}-\cdots – b_0) =0 \) より、\(a\neq 0\) だから、\(x\) は \(R\) 係数の単多項式 \(x^m-b_{m-1}x^{m-1}-\cdots – b_0=0\) の解である。\(R\) は整閉なので \(x\in R\) を得る。したがって、\(P^{-1}\subset R\) となり、これは補題2に反する。
(定理1) \((0)\) または \(R\) でない整イデアルは素イデアルの積に(順序を除いて)一意的に分解される。
(証明) 補題1より、整イデアル \(I\) に対して、\( P_1\cdots P_r \subset I \subset P \) となる素イデアル \( P,P_1,\cdots,P_r \) が存在する。\(r\) に関する帰納法で素イデアル分解ができることを示す。\(r=1\) のとき、\( P_1 \subset I \subset P \) である。\( P,P_1 \) は極大イデアルだから、\(I=P=P_1\) となる。\(r>1\) とする。補題2の証明の通り、\(P_i=P\) となる \(P_i\) が存在する。\(P_r=P\) とすると、\( P_1\cdots P_{r-1}P \subset I \subset P \) から \( P_1\cdots P_{r-1} \subset P^{-1}I \subset P^{-1}P=R \)。\( P^{-1}I=R \) ならば \(I=P\)。\( P^{-1}I \neq R \) ならば、帰納法の仮定より \( P^{-1}I \) は素イデアルの積で表すことができ、\( P^{-1}I =Q_1\cdots Q_s \) とすると、\( I=PQ_1\cdots Q_s \) となり、素イデアルの積で表される。
一意性を示す。\( P_1\cdots P_r = Q_1\cdots Q_s\,(r\leq s) \) とする。\( P_1 \subset P_1\cdots P_r = Q_1\cdots Q_s\) だから \(P_1=Q_i\) となる \(Q_i\) が存在する。順序を入れ替えて \(Q_1=P\) としよう。すると、\( P_2\cdots P_r = Q_2\cdots Q_s \) となる。これを繰り返すと、\(P_i=Q_i \,(1\leq i\leq r) \) を得る。\( r<s \) とすると、\( R=Q_{r+1}\cdots Q_s \subsetneq R \) となり矛盾。よって、\(r=s\) となり、素イデアル分解の一意性が証明された。
分数イデアル \(I\) は負冪を含めた素イデアルの積に分解される。\(\gamma I = J\) となる \( \gamma\in R \) と整イデアル \(J\) が存在する。\( (\gamma)=P_1\cdots P_r, J=Q_1\cdots Q_s \) と素イデアル分解をすると \( P_1\cdots P_r, I = Q_1\cdots Q_s \) となるから、\( I=P_1^{-1}\cdots P_r^{-1} Q_1\cdots Q_s \) と素イデアル分解できる。
分数イデアルの整除性
整イデアルに \(I,J\) について、\(I \vert J \Leftrightarrow I \supset J \) であった。これが分数イデアルに拡張できることを確認する。分数イデアル \(I,J\) について、\(I \vert J \) とは \( J=IA \) となる整イデアル \(A\) が存在することと定義する。\(I=\frac{I_1}{I_2}, J=\frac{J_1}{J_2}\) とすると、\( J_1 I_2 = I_1 J_2 A \) より \(J_1 I_2 \subset I_1 J_2 \) となる。 これより、\( I=\frac{I_1}{I_2} \supset \frac{J_1}{J_2} = J \) を得る。
参考文献
代数的整数論入門(上) 藤崎源二郎 裳華房
数理・情報系のための整数論講義[増補第2版] 木田雅成 サイエンス社