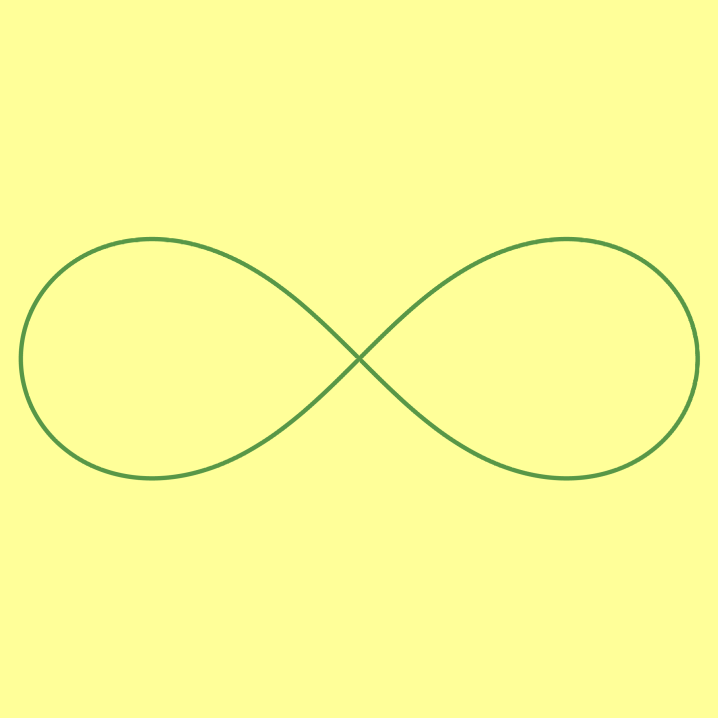修論の審査は発表会(公聴会)と最終審査の2つのプロセスを経るのが正式らしい。多くの大学では発表会が最終審査を兼ねていると思われるが、最終審査は密室での審査になるべきであり、2つを兼ねるのは正しくないようだ。本学では珍しく2つのプロセスに分かれていた。しかし、セッションが並行に実施されていたことが問題だった。4セッション以上だったと思う。教員は審査を担当しているセッションしか出ない。担当していないセッションに出ることはもちろん可能だが、ほとんど出ることはない。学生も所属研究室か親しい同級生の発表しか出ることはなかった。
ある時、修論発表会のセッションを1つにして教員は所属学科のすべてに出席せよと、学部長から指令が下った。元々、学部長は学科だけでなく工学部全ての発表を聞くのが教員の責任と主張していた。工学部という線引きがどこから出てくるのか全く疑問であった。線引きは学科でも全学でも可能なはずで、学部という根拠が分からなかった。今回の指令は学部長の思想からではなく、文科省からの指導のようだった。全員の発表を1セッションで実施するのは日程的に無理があった。2セッションを並行して実施し、教員は一方のセッションに出席することを義務付けることにした。要請には完全に応えていないが、努力姿勢を見せたところであろう。最終審査は発表会が兼ね、要審査と判断した場合のみ最終審査会を行うこととした。
ある教員が学科会議で学生も全ての発表を聞くべきだと言い出した。その主張が有益なら、これまででも所属研究室の学生に他の研究室の発表を聞きに行くように指導することは出来たはずだ。それを行わずに教員に義務付けられた途端に学生にも求めるのは単なる腹いせにも思える。本当に学生の事を考えての意見だろうか。教員は学生を縛り付けたがる。縛り付けておかないと自堕落になる傾向にあるため、研究室に来させる習慣はある方が良いとは思う。しかし、発表会に縛り付けてもあまり意味はないのではないか。私は研究室のM1には発表会を聞くように勧めている。それは翌年の発表の参考になるからだ。就職直前で発表会を聞いても、それが社会に出て役立つのだろうか。私は反対した。学科会議では私の意見が認められ、学生には強制しないことになったが、後日この決定は無視されてしまう。
同じ教員が今度は修士の中間発表の時期を変更する提案をした。従来は9月に行っていたが、確かに遅すぎる。これでは中間発表で指摘された事項を修正する時間が短すぎるからだ。しかし、提案してきたのはM1の3月末。早すぎる。修士課程は学部からの進学者だけではない。研究室を変更した学生もいて、研究の基盤作りから始めなければならない学生もいる。響研究室では、その時期には研究テーマすら決まっていなかった。変更時期の理由は「中間だから2年間の真ん中でなければならない」と言う。「それでは博士課程はD2の9月に中間発表をしなければならないではないか」と反論した。博士課程の中間発表は、論文または国際会議論文の採録決定後なので多くが間に合わない。しかし、訳の分からない反論が返ってくる。博士の中間発表時期は遅くて良い理由を主張していたようだったが、理解できなかったので何を言われたのかは憶えていない。